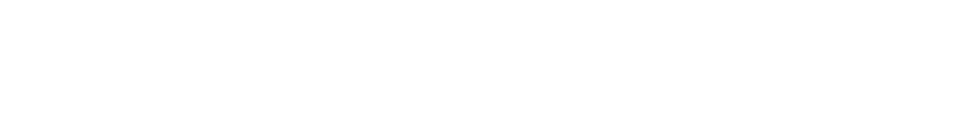新型コロナウイルスの影響により、会社での人間関係の構築が難しくなっているという声が聞こえてきます。特に新人は、仕事を覚える間もなくリモートワークが推進され、本人も指導する側も戸惑いを抱えています。メルマガ『毎月1000人集客するプロ講演家が教えるコミュニティづくりの秘訣』の著者で、ベストセラー作家・起業家の岡崎かつひろさんは、新人教育のキーワードとして、ティーチング、コーチング、ホーチングを上げ、特に「ホーチング」には注意が必要とアドバイスしています。
【関連】実はコスパ最強?YouTube広告「5秒ルール」が認知度UPに使えるワケ
会社での人間関係って必要?
「職場における人間関係が大事」という話は、耳にタコができるほど聞いたことがあるかと思います。本当にそうなのでしょうか?
なぜ職場の人に好かれたほうがいいと思いますか?仕事仲間なのに好かれる必要ってあるのでしょうか?仕事上関わりがあるとはいえ、自分がやるべきことさえやっていればコミュニケーションを取らなくても特別問題ない。そんなふうに感じること、ありませんか?実は、これはかつての僕自身が考えていたことです。
今は、人に好かれなくてもなんとかなる時代なんです。今の時代の特徴として、人から好かれることよりも個性重視に走ってしまっているところがあります。これは、僕は学校教育が原因じゃないかと思うんです。これまでゆとり世代は「個性を豊かにしよう」といっていたわけですよね。
そのときに「詰め込み型の教育をやめよう」ということで、個性を尊重して、自由にイキイキ学ばせられる環境を作ろうとしていたわけです。ところが蓋を開けてみたら、個性的なのは外見ばかりで思ったよりも中身が育っていなかった。中身のない人をたくさん作ってしまったんじゃないかと思います。
インプットなきアウトプットは伸びしろが決まってしまう
僕は、その人の人間性はインプットの量で決まると思っています。人から教わって、たくさんの情報をインプットしたことではじめてアウトプットができる。
教育の世界でよく言われるのは、ティーチングがあって、初めてコーチングがある。コーチングで「どうしたいの?」「なにが問題だと思う?」と繰り返し質問をうけることで、これまでだったら人から尋ねられないときづかなかったことを、今度は自分に問いかけることで、自分自身で気がつけるようになる。そうすると人は育っていくと思います。
たとえば、新入社員が入社して、仕事をおぼえていないのに自分のやり方でやりたいと言い出します。上司から見たら「新入社員なのに、自分なりのやり方で仕事を進めようとしたら成果は出せないよ」ということです。それで「これをやれ」「あれをやれ」というと、「納得いきません」「やらされている」といって会社を辞めてしまう。会社に対するロイヤリティと、会社の仕事に対する情熱が失われていき、ただそこに座っているだけのダメ社員ができてしまうのです。
コーチングの前にまずはティーチング
もしも自分が新入社員の立場であれば、まずは言われたことをちゃんとやり、ベースになる能力を身につける。上司も部下をティーチングしてからコーチングする。たとえば、「○○君、この仕事をどうしたらいいと思う?」「今、起きている問題で何が問題なのかな」「○○君がもっとうまくやるためにはどうしたらいいと思う?」という質問は、コーチングですよね。
ただ、世の中でコーチングを重視するため、ティーチングがおろそかになってしまっています。そうなると、新人の能力が追い付いていない。知識もない。判断基準も持っていない。そんな人に「自由にやれ」といっても、難しいですよね。
「新人指導をしない」“ホーチング”上司が担当になったら
ひどい上司になると「新入社員に自分で考えてやれ」という。「仕事は盗むもの」だといって指導をしない。しかし、本当は上司自身、教え方がわからないのです。じゃあ、なぜ上司は教え方がわからないのかといえば、自分も教えてもらっていないから。そんな状況が続いているから、「仕事は盗むものが当たり前。自分で考えない」といって後輩の指導をしないのでしょう。
結果的には、新人社員は何の土台もないまま放置されることになります。新入社員にとってもストレスですよね。教える人も教わる人もストレス。前はコーチングというよりも、放置。「ホーチング」ですよね!「ホーチング世代」は常にホーチングをしてしまうんですよね。
コミュニケーションを取らなくても仕事は回る
話がズレましたが、なぜ人に好かれなくても仕事ができる時代になってしまったのかといえば、ルーティン化された作業が多くなってきたからです。今の時代、新しいことをしなくてもなんとかなってしまうのです。
僕らの上の世代の人たちは、働く仕組みを整えてくれました。そのおかげで、今僕たちはまわりの人に好かれなくても決められたことを決められたとおりにやれば済む時代になってきました。
以前は、上司から仕事を聞き、あちこちに根回しをしないとうまくいかないこともありました。しかし、今の時代、業務がシステム化され、“ノミニケーション”をしなくても仕事がまわるようになってきたのです。
しかも、上司の側から「一緒に飲みに行こう」と誘うと「アルハラ(=アルコールハラスメント)」だといいだす面倒くさい人たちもいます。だから上司も下手に部下を食事や飲みに誘えなくなってしまったのです。そういうところでコミュニケーションロスが発生していることも多いと思います。
これは「誘われたくない部下」「仕事以外でコミュニケーションを取りたくない部下」からしたら、非常にいいことだと感じるかもしれません。しかし、反面これによってコミュニケーションロスが発生しているのも事実です。
それでもあえてコミュニケーションを取る理由は?
仕事において、そのままでいいのであればコミュニケーションはいらないと思います。
というのも、ビジネスは働くレイヤーというのは3層あります。1つは組織全体の方向性を導くトップマネジメント。
次に、マネージャー、マネジメント層で、中間管理です。中間管理の人たちは上から伝えられたことをかみ砕いて、実行部隊に意味や価値、具体的なやり方を指示する必要があります。
最後に、いわゆる実行部隊は何をやればいいのか明確にやればわかりさえすれば、動くことができます。いわれたことをちゃんとやる。
実行部隊でいる限りは「なにをやるか」という指示がちゃんとわかればいいわけです。そのため、まわりから好かれていようが好かれていないだろうが、言われたことをちゃんとやればそこにとどまれるわけです。
中間管理職。仕事力とともに対人スキルが必要なワケ
中間管理職の人は、上から来た指示を理解して、わかりやすくかみ砕き、実行レベルまで落とし込む必要があります。中間管理職の人間関係は、主に2つ。まず1つは上司との関係。もう一つは部下との関係。
上司から信頼されていて、良好な人間関係が築けていれば、指示がわかりにくいときに「どういうことですか?」と聞けますよね。逆に、関係性が悪いと、そもそも「どういうことですか?」と質問ができない。聞けたとしても「お前が自分で考えろ!」と突き放されます。当然、上司から好かれていて、かつ信頼されていた方がいいですよね。
中間管理職、求められるのは人間性の高さと信頼感
結局、コミュニケーションは好かれるだけでは前に進みません。「あいつ、いいやつなんだよね」と好かれるのと、「あの人は信頼できるから仕事を任せたい」といわれるのは別軸です。
好かれる人というのは、明るかったり、前向きだったり、見た目に清潔感がある。こういう人は好かれますよね。
これに対して、仕事において信頼される人は、約束を守ったり、期日を守ったり、期待されたこと以上の仕事をやることです。そういう人は、仕事において信頼されます。
ただ、「こいつはちゃんと仕事をやるんだけど、いちいち言い方が頭にくる」という人は、好かれはしないけれど仕事上は信頼されているわけです。信頼されているだけでもいいとは思いますが、できればまわりの人から好かれていて、信頼されている状態にまでもっていきたいじゃないですか。そのほうがお互い気持ちよく仕事ができるわけだから。
反面、「会社においてコミュニケーションを取る必要がない」と思っている人は、「仕事上で信頼だけされていれば、わざわざコミュニケーションなんか取る必要はない」と、そう思っているのでしょう。というか、かつての僕自身がそう考えていました。
ようは、上からきた仕事をちゃんと一度自分でかみ砕いて理解しなければいけないとなると、かみ砕くだけの情報提供がないとできません。必要な情報をちゃんと上から提供してもらうためには、上との信頼関係と好かれている状態を作り出すことが大切です。(メルマガより一部抜粋)
※本記事は有料メルマガ『毎月1000人集客するプロ講演家が教えるコミュニティづくりの秘訣』2020年10月24日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会に初月すべて無料のお試し購読をどうぞ。
- 「会社での人間関係って必要?」2020.10.26 /vol.62 62号(10/24)
- 「組織の拡大におけるコミュニティ運営。方向性の違いをどうとらえるか」2020.10.24 /vol.61 61号(10/19)
- 「意識の違いから別々の道へ。今いる組織から独立を考える時」2020.10.12 /vol.60 60号(10/12)
- 『マンネリ化しないコミュニティ運営のコツとは?』2020.10.10 /vol.59 59号(10/5)
- 「コロナ禍でも会いたいと思われる人になる」2020.9.29 /vol.048 48号(9/29)
- 『チャンスはつかめる者の前にしかやってこない』2020.9.21 /vol.057 57号(9/21)
- 「人が集まるところには自然とお金も集まる」2020.9.17 /vol.056 56号(9/17)
- 「目標達成の可能性が今の3倍も高まる「If-then 方式」2020.9.12 /vol.055 55号(9/7)
- 『自然と人が集まってくる人の特徴は?やるべきこと、やってはいけないこと』2020.8.27 /vol.054 54号(9/1)
- 『声をかけても人が集まらない。原因は?』2020.8.17 /vol.053 53号(8/17)
- 『読者相談:オンラインクッキング教室を始めたい。集客で注意すべきことは?』2020.8.10 /vol.052 52号(8/10)
- 『広告費をかけずに認知度を上げる「YouTube広告5秒のルール』2020.8.4 /vol.051 51号(8/3)
image by: Shutterstock.com