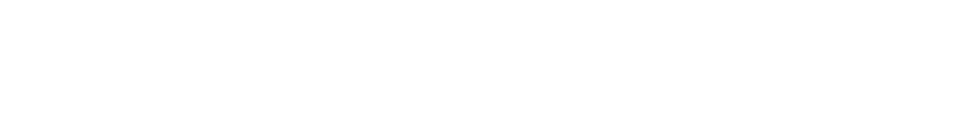新型コロナウイルス感染症の収束時期が見えず、先行きが不安な状態が続いている日本経済。この状況下の中、さまざまな手を使って正社員のリストラを断行する企業も増えているのが現状ですが、中でも悪質なものが「業務委託契約」への切り替えを強制する手口です。メルマガ『ブラック企業アナリスト 新田 龍のブラック事件簿』の著者で働き方改革コンサルタントの新田龍さんは、従業員にメリットの部分もある「業務委託契約」を悪用し、リストラや減給の代わりに利用しているブラック企業の実態について、実例をあげながら詳しく紹介しています。
【関連】専門家が教える「退職勧奨」不良社員をモメずに追い出す方法とは(台本付き)
【関連】1500人もの社員を「適法」でクビにした日本IBM「退職勧奨」の実態
社員を「業務委託」契約に変更させて働かせるブラック企業の実態
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、我が国の雇用環境は劇的に変化した。厚生労働省の発表によると、コロナによる解雇や雇い止めは8万8千人を超え、雇用調整の可能性がある事業所も全国で12万箇所超となっている(2021年2月19日現在)。ただこの数字はあくまで国が把握している人数に過ぎず、実際の失業者数はさらに多いとみられる。
● 新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について(厚労省) ※PDFが開きます
また、大手企業でさえ希望退職を募るほどコロナの影響は大きく、2020年上場企業の早期・希望退職は93社にのぼり、これはリーマン・ショック以降では09年に次ぐ高水準だ。
● 2020年上場企業の早期・希望退職93社 リーマン・ショック以降で09年に次ぐ高水準(東京商工リサーチ)
そんな大々的なリストラ渦中において、解雇や雇い止め、早期退職ほどは報道される機会がないものの、着実に進んでいるブラックな手口が存在する。それが「業務委託契約の悪用」だ。
これは、正社員の雇用契約を業務委託契約に切り替えたり、最初から業務委託契約で人を募集したりして、彼らに個人事業主として会社の仕事を請け負ってもらう、という手段である。
業務委託契約のメリット
ただし注意が必要な点がある。先ほど「ブラックなリストラ手口」と言い切ったが、「業務委託契約」自体は何の問題もない合法的なものだ。正社員から業務委託契約への切り替えについても、働き方改革の一環として一部大手企業などで数年前から導入されている。
もちろん、働き手にとってのメリットもある。雇用されるという立場ではなく、独立した事業主として仕事をしていくため、
- 自分で仕事を選べ、自身の都合に合わせたスケジュールを組めるなど、従前の会社の枠組みにとらわれない、自由と裁量が多い働き方が実現できる
- 労働時間の制限がないため、働けば働くほど収入も増え、働きが報われる
- スキルアップにかける費用などを経費計上でき、節税メリットと手取り収入の増加に繋がる
といった点がプラスの効果として挙げられる。実際、導入済の企業においては契約を切り替えた個人事業主の手取りが増えたり、新たな仕事が生み出されたりするなど、会社と働く側、双方にとって相乗効果が出ている事例もあるようだ。
今後、企業において「70歳までの雇用努力義務化」が進められることになっており、企業が採るべき選択肢の一つとして、「継続的に業務委託契約を締結する制度の導入」が挙げられているので、この方法は定年後の雇用施策としても有効と考えられる。適正に運用されれば、これからの時代における新たな働き方として進展が期待できるはずだ。
業務委託契約のデメリット
しかし、メリットがある一方でデメリットも存在する。懸念の声としてもっとも多く挙げられるのは「業務委託契約で働く人は、労働法に守ってもらえない」ことだ。すなわち、自由である反面、保護が弱くなり、すべてが「自己責任」になってしまう。これこそ、リストラ手法として懸念される理由でもある。具体的には、
- 雇用契約(正社員)であれば労働基準法等で守られる、労働時間、賃金額(最低賃金額や割増賃金額)、賃金支払いの原則(全額払いや、毎月1回以上一定期日払い等)、休日休暇といった各種保護が存在しない
- 厚生年金や雇用保険、福利厚生など、会社からの保障が一切なくなり、必要であれば自ら手続して支払いする必要がある。交通費や諸経費も自己負担となる
- 取引先都合により、急に仕事が打ち切られたり、報酬金額を下げられたりするリスクが常に存在する
このように、「会社対従業員」といういわば主従関係から脱せられる代わりに、「会社対取引先」という関係性に変わることで、より個人の責任範囲が大きくなってしまうのだ。
働く側がメリット・デメリット双方を理解し、企業側が制度を適正に運用していれば、世の中全体としてもメリットの大きい業務委託形式。それでも、弁護士など専門家から懸念の声が挙がるのは「適正に運用しない企業」が存在するからに他ならない。
悪意ある企業は、「法律の規制と社会保障負担を免れる」という企業側だけにメリットのある部分だけをつまみ食いし、一方で正当な報酬を支払わず、いわば「自社の下請」として使い潰そうとする。場合によっては先述のように、「リストラの手口」として悪用されることもある。しかも残念なことに、働く側も法律を詳しく知らないため、悪意ある企業の言いなりになってしまうという不幸なケースも散見される。
仮に、会社側と働く側がお互いに契約内容に合意して業務委託契約を結んだとしても、その働き方や仕事の進め方が社員と変わらず、実態として「働く側が企業側に従属して使われている」と判断されれば、その契約は違法となり、会社側は処罰の対象となるのだ。では、どんな条件だとダメなのか。
- 仕事自体の自由がない(仕事を断れない、競合企業からの仕事受託を禁止される等)
- 働く時間や場所の自由がない(勤務時間や出社場所の指示・拘束がなされる等)
- 仕事の進め方の自由がない(仕事の手順や進め方を管理される等)
このように、「業務委託契約でありながら、実質的に社員と変わらない勤務を要求される」状態はいわゆる「偽装請負」であり、違法だ。契約条件については事前に充分な確認と注意が必要なのである。
業務委託契約を悪用したブラックな事例
「偽装請負」として真っ先に想起される働き方としては、IT業界における「SES」が挙げられるだろう。SES(システムエンジニアリングサービス)とは、客先のオフィスにシステムエンジニアを派遣してソフトウェアやシステムの開発、保守、運用業務を受託する契約のことだ。
派遣されるエンジニアは派遣元企業の正社員であり、本来であれば契約上、指揮命令権は雇用主(派遣元)のSES企業にある。しかし実態として、エンジニアたちは顧客企業(派遣先)からの指示で動くことが殆どであり、これは違法な偽装請負にあたるのだ。本来自社が持つべき指揮命令権を客先に奪われてしまえば、自社の義務である労務管理などまともにできるはずがない。にも関わらず、客先とエンジニアの間に入ってマージンだけを得る。まったく存在価値のない、ブラックな業種だと言い切ってよいだろう。
同じような構図は、医療業界にも存在する。たとえば「O歯科医院」(東京都)では、訪問歯科診療の提携先を開拓するために別会社「T株式会社」を設立。O歯科医院で正規職員として勤務していた社員AをT社の開拓営業に従事させたのだが、その際に出向や転籍をさせるのではなく、社員AにT社との「業務委託契約」を結ばせたのだ。業務委託であれば、Aは個人事業主として自由な裁量で仕事ができるはず。しかし実際のところ、AはT社代表者から細かく指揮命令を受け、ノルマ設定や残業強制までなされていた。これでは実質的に労働者と何ら変わらず、O歯科とT社のやり口はまさに違法な偽装請負といえる。
またT社では求人サイトに営業募集広告を掲載していたのだが、本来成果報酬しか存在しない業務請負契約を結ぶにもかかわらず、そこには「お給料は基本給と歩合」「裁量労働制 09:00~17:30」と堂々と記載されていたのだ。いずれも業務委託とはまったく異なる概念であり、基本的な法律さえ理解していないブラック企業といえるだろう。
全国でリラクゼーションサロン事業を展開している「株式会社B」(東京都)もまた、業務委託契約を悪用している会社のひとつだ。同社のセラピストは業務委託契約で採用され、採用ページを見ると「リラクゼーションセラピスト」「リラクゼーションスペースでのお仕事」と曖昧な記載しかない。一見する限りでは、セラピストとしての技術提供と接客によって出来高制の報酬を得られるように受け取れ、法的にも問題ないように映るのだが、内部関係者の告発によると、実質的にはB社の指揮命令下で労働者としての業務遂行を求められ、違法性が疑われるという。具体的はこのようなものだ。
- 「業務委託契約なので雇用関係は存在しない」という建前だが、セラピストは店舗のシフトに合わせて勤務する必要がある他、開店・閉店に伴う事務作業、清掃や電話応対、報告書作成など、施術以外の業務にも対応する必要があることから、実質的な労働者性が疑われる
- 業務委託費用は施術時間に準じているため、施術以外の店舗運営業務に従事している分にはセラピストに収入が発生しない仕組みとなっている。また、業務委託でありながら休日取得やシフト変更に了承が必要であったり、身だしなみにも仔細なルールが存在したりするなど、労働者並の拘束が存在している
- 「無料」と銘打っている研修についても、テキストや検定料、実際に店舗で客として施術を受けるといった実費負担が多く、研修後一定期間内に退職した場合は、1受講科目あたり数万円の研修費用を支払わなければならない
業務委託であるにも関わらず、細かい指示をおこなって社員のように都合よく使い、一方で雇用関係にあれば一般的に会社が負担する研修費用などは実費請求する。まさに、業務委託の都合の良い部分だけを得て、リスクを働く側に押し付ける、悪意あるやり口といえるだろう。
会社から「業務委託に切り替えないか」と言われた場合の留意点
(1) そもそも、独立した個人事業主としてリスクをとれない人は受けるべきではない
業務委託契約におけるメリット・デメリットは先述のとおり。「会社の枠に縛られずに自由に働ける」ということは、裏を返せば「会社と法律には一切守ってもらえないので、自分の身は自分で守るしかない」ということになる。業務委託契約は成果物に対して報酬が支払われるため、たとえ報酬に見合わないほどに労働時間を費やしてしまっても、受け取れる報酬は成果物に対するものだけだ。
当然、時間管理も体調管理も自己責任となるし、「業務委託のほうが報酬は上がるよ」などと約束されても、保険料などの持ち出しも増えるし、いつその約束が反故になるか分からないという不安定感と隣り合わせだ。それでもチャンスだと考えられる場合に限って受ければよいだろう。
(2)業務委託契約への転換を強要するのは違法
大前提として、業務委託契約を新たに結ぶ場合、働き手への保護・保障の度合いが大きく異なり、仕事の進め方等の面でも違いが存在するため、会社側はそれらについて細かく説明する義務があるし、働く側との合意も必要だ。
しかし、あなたを使い潰そうという悪意がある会社の場合、説明を充分おこなわなかったり、「業務委託契約を結ばなかったらクビだ」などと強要してきたりする可能性がある。しかしそれは違法なので、あなたが不安を感じた際は「会社側からの業務委託契約の申出は断ることができる」ことを知っておいて頂きたい。
(3)働く側に不利にならない条件を要求する
業務委託のリスクも把握したうえでチャレンジする場合、リスクや不安点はできる限りすべて払拭でき、不利益のない契約内容となるようじっくり話し合うことをお勧めする。
- 正社員勤務時代の収入を基に、保険料支出なども踏まえた手取り収入水準を維持できる報酬設定にする
- 契約期間を長期に設定し、その期間中は一定量の発注を継続することを条件とする
- 「契約から3年間は競合企業との取引禁止」といった、将来的に不利に働く可能性がある契約条件は削除を要求するか、禁止期間を短くしてもらえるよう交渉する
といった形で、双方にとってメリットのある形を考えていければよいだろう。
(4)業務委託契約後も、労働者性が変わらない場合は
先出のトラブルケースのように、業務委託契約なのに発注元企業の指揮監督下に置かれ、労働者と何ら変わらない労働条件のまま働かされる可能性がある。その際は、当該契約は実質的に雇用契約であると判断され、労働基準法の適用を受けることになるため、発注元企業に対して残業代や未払い賃金を請求することが可能となる。そのような指示にまつわるメールや文書等の証拠を確保したうえで、きちんと請求すべきだ。
このように、本来は企業と働き手双方にメリットのある働き方が実現できる可能性がある業務委託契約。一方で、悪意ある企業が強要すると一転して、働く側のデメリットにもなるリスクがある。ブラック企業の悪意には重々留意しつつ、もしあなたにとってメリットのある働き方を実現できるのであれば、選択肢として検討してみる価値はあるだろう。
※本記事はメルマガ『ブラック企業アナリスト 新田 龍のブラック事件簿』の発行者、新田龍さんがMAG2NEWSに書き下ろしたオリジナル記事です。2021年3月中のお試し購読スタートで、新田さんのメルマガの3月分全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます。
【関連】法律で守られたはずの正社員を次々クビにする日本企業の恐ろしいカラクリ
<こちらも必読! 月単位で購入できるバックナンバー>
※初月無料の定期購読のほか、1ヶ月単位でバックナンバーをご購入いただけます(1ヶ月分:税込330円)。
- 【Vol.031】あの企業の知られざる実態/コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?(その5)(2/12)
- 【Vol.030】あの企業の知られざる実態/コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?(その4)(1/8)
- 【Vol.029】あの企業の知られざる実態/コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?(その3)(12/11)
- 【Vol.028】あの企業の知られざる実態/コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?(その2)(11/13)
- 【Vol.027】あの企業の知られざる実態/コロナ禍で人員削減、実際どうやってクビを切っているのか?(その1) (10/30)
- 【Vol.025】今の会社、「心配ないパターン」と「要注意パターン」一覧 (9/11)
2020年8月配信分
- 【Vol.024】「ジョブ型雇用」は万能の特効薬ではない/文春オンライン、スキャンダル報道の裏に潜む「大人の思惑」(8/28)
- 【Vol.023】テレワークのコミュニケーションにまつわる不安を解消する方法/「日本郵政グル
ープ」で起きた労務トラブルもみ消し事件(8/14)
2020年7月配信分
- 【Vol.022】東京女子医大病院「400人退職」騒動その後/「四大法律事務所」の一角でトラブル続出の事態に(7/24)
- 【Vol.021】テレワークで剥がれた“化けの皮”/森・濱田松本法律事務所が労務トラブル揉み消
しでもトップブランド(7/10)
2020年6月配信分
- 【Vol.020】日本人の「給料安すぎ問題」について/明治安田生命保険相互会社、実はテレワークに後ろ向きなマインドの会社(6/26)
- 【Vol.019】「パワハラ防止法」が6月1日より施行!/「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰」受賞企業の明治安田生命保険相互会社の疑惑(6/12)
2020年5月配信分
- 【Vol.018】ロイヤルリムジン「乗務員600人全員解雇」騒動のその後(5/22)/明治安田生命保険相互会社テレワー
ク可能な従業員にも強制出社(5/22) - 【Vol.017】コロナは災害だが、「働き方改革の進展」はプラス影響/Yahoo!ニュース、誤認を認識しながら故意に偏
向報道をした疑惑(5/8)
2020年4月配信分
- 【Vol.016】緊急事態下でも、働く人が身を守るために使える制度とは/Yahoo!ニュース、「事実誤認記事」掲載で炎上した事業者が
破産(4/24) - 【Vol.015】緊急事態宣言と、ロックダウンできない日本/ハウスメーカー業界首位、「大和ハウス」のブラック体質(4/10)
2020年3月配信分
- 【Vol.014】大スクープ連発の週刊文春、圧倒的強さの秘密/SMBC日興証券の「新興国為替仕組債」勧誘販売で問題続出、一般投資家被害額は2,000億円超か(3/27)
- 【Vol.013】新型コロナウイルスで雇い止めや給与カットするくらいなら育休
をとらせよ/「昔からブラック!!」「今はホワイト!?」証券営業の実態(3/13)
image by: Shutterstock.com