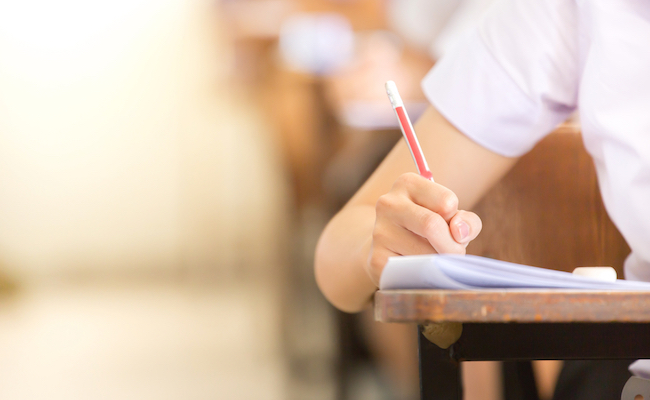そして、誤解を恐れずに言えば、一番、不可解に感じるのは、「ケース会議」です。もちろんワンチームになるため、目標を明確化することが目的なのですが、いじめがあったと認めたうえでのケース会議は、利益相反する人をメンバーとするという、ストレスフルな状況をつくり出すこともあります。ときには不参加という残念な結果をもたらすことがあります。学校組織における意思決定者は校長ですので、校長が不在であれば、会議そのものが意味を持ちません。また、守秘義務とそれぞれの職責との兼ね合いは、いかがでしょうか。つまり、ケース会議と言っても、ピンからキリまであるということです。
介護のためのケース会議では、病状やかかりつけの医師などの情報共有が大切です。サービスの契約なので本人の意思は明確です。反対に、非行・犯罪や児童虐待のために集まるケース会議のメンバーは、それぞれ専門家で公務員であり、守秘義務は守られ、問題を解決しようというタスク機能があります。個人情報を取りあつかう明確な根拠があります。
一方、いじめ問題では、高い人権意識が求められます。被害児童をケース会議の中心に置く、つまり、被害を受けている子に、どのようにアプローチするかという観点や、被害児童がなぜいじめられたか、被害児童の家族関係などといった観点から会議をすると、児童やその家庭の了解を得ないまま、プライバシーを話し合うことにもなりますので、非常にあやういのです。しかしながら、この場に、児童委員や民間の組織を参加させるには高い壁があります。また、だれがどのように職責を果たすのか、不明瞭です。
その結果、「被害児童の家庭に問題がある」、「本人がおとなしすぎる。性格の問題だ」などと、いじめられた被害者に責任があるとされてしまい、「様子を見ましょう」とか、「被害者をサポートしていきましょう」などという提案がなされ、結果、「いじめは解決しない」ということになります。
これまでの経験では、ほとんどの場合、「加害児童」やその家庭をケース会議の中心議題に置くというのは見たことがありません。加害児童は指導されることもなく、通常のごとく登校し、家庭での不満を学校で解消し、いじめを繰り返します。被害児童は、不登校になります。被害児童を中心に置くと、学校は「楽」なのです。加害児童に対しての指導スキルのない学校では、対応に困りますから、被害児童を中心に置きたがるのです。
けれども、本来の教育の使命、つまり加害児童を反省させ、謝罪に持っていくためには、教育的な力量や経験が必要です。それは先生の仕事なのです。
実際のところ、いじめが起きた小学校で、効果が上がった方法は、
1 予算をつけてもらい補助教員を採用する。または、シフト体制をとり別の教員(OBでもよい)に応援にきていただく
2 クラスを半分に分けたり、教科別に生徒をわけたりして、加害者と被害者の学習環境をわける
3 毎日が学校開放日(つまりは授業参観)とし、PTAや保護者に教室にお越しいただき、大人の眼がつねに光っている状態にする
4 スクールソーシャルワーカーは、休憩時間には、すすんで子ども達の遊びに入り見守る(自然な形で被害者のガードをする)
5 PTAや地域の方々の協力を得て、登下校時には大人が子ども達と一緒に歩く
上記は一例ではありますが、このような方法で、これまでの環境をかえて、子ども達が静かに学習でき、運動や遊びができるようになりました。子ども達の心も安定し、いじめはなくなりました。
これらを決断し、教育委員会を動かし、保護者にはたらきかけたのは、校長先生です。そして、校長先生を支えたのは、決してあきらめない、教育の使命を知る良心的な教員たちでした。大切なことは、手順や方法ではありません。いじめから被害者を守り、いじめられない環境をつくり出すことなのです。スクールソーシャルワーカーは影の根回し役でよいのです。
子どもをいじめから守るのは、保護者、親のつとめです。そして、学校で、いじめを解決するのは、先生なのです。それを忘れないでください。
いじめを解決する相談を受け付けています。ご遠慮なくご連絡いただければと存じます。
社会福祉士・精神保健福祉士
元保護観察官
前名古屋市教育委員会 子ども応援委員 SSW
現福祉系大学 講師 堀田利恵
image by: Shutterstock.com