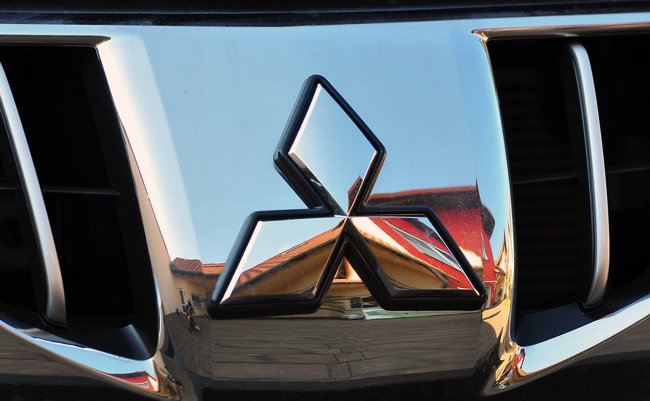これまでのところ、わりと結構、好意的というか、むしろ、とても良いことという見方が主流になってるような印象だ。
「日産がスキャンダルに襲われた三菱に命綱を投げた」
(Nissan Throws a Lifeline to Scandal-Stricken Mitsubishi)
とか、
「日産が三菱自動車にライフラインする」
(Nissan lifeline for Mitsubishi Motors)
とか、
「驚きの命綱」
(a surprise lifeline)
などと、やたらに「命綱」(lifeline)という単語が名詞としてだけでなく、動詞としても使われてる例を、あちこちの記事で見かけておもしろい。
日本語では、あまり「命綱」のような表現を経済ニュースの真面目な記事では見かけない気がするけど、どうやら英語では、これが、こういう時の定型句なのかも?
窮地に陥った三菱自動車を日産が救世主のように救いにあらわれたという感じの取り上げ方になっていることから、「命綱(lifeline)にはポジティブな意味合いが含まれているのかもしれない。
うーむ。
海外のメディア関係者の方々も、三菱財閥グループが特別な存在であることは、さすがに一応、分かってはいるが、日本国内ほど、その特別さについてこだわりがない、ということか?
また、海外のメディアは、日本国内のメディアよりも、もっとグローバルな視点に立って、今回の日産・三菱の資本提携の一件を分析している気がする。
そう、グローバルな視点。
それが日本国内の報道とは大きく違う。
日産・三菱という、日本の大きな自動車メーカーというか、日本を代表する大企業のお話なので、ついつい、うっかり、日本国内の状況に目を向けがちだけれども、実は、日産も三菱も、すでにかなりのグローバル企業になっている。
実際、近年の自動車産業は、主にアメリカ、ヨーロッパ諸国、日本の大手メーカーが、世界を舞台に競い合っていて、それぞれ外国に大規模な生産拠点を持ってることも珍しくない。
日本車だからといって、全部、日本で作ってるわけじゃないのだ。
重要な部品は日本国内で作っていても、それを組み立てるのは、アメリカ国内でアメリカ人がやってたりする。
そう言えば、2009~10年に、アメリカでは、運転中に発生した急加速事故の原因がトヨタ車にあるということで、大リコール問題が発生し、トヨタ自動車が、アメリカの生産拠点での製造の様子を中心にしたテレビCMを放映したこともある。