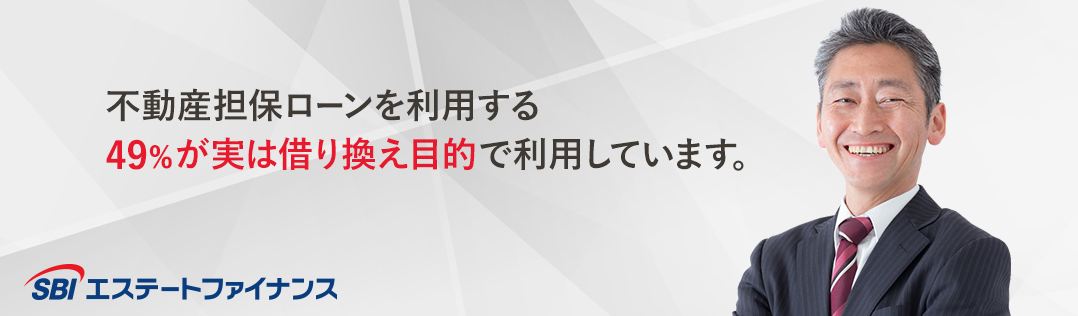相続時精算課税制度は、両親や祖父母から財産の贈与を受けるときに選択できる制度です。この制度を利用することで、贈与時の負担軽減につながる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度にはデメリットもあるため、制度の内容を理解した上で利用を検討することが大切です。今回は、相続時精算課税制度の概要やメリット・デメリットを紹介します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。同一の贈与者からの贈与であれば、2,500万円まで贈与税は課税されず、限度額に達するまで何回でも控除でき、限度額を超えた部分については、一律20%の贈与税率が適用されます。
また、相続時には、相続時精算課税制度の贈与財産と他の相続財産と合計して相続税を計算します。贈与税を支払っている場合は、相続税から支払済の贈与税を差し引くことができます。
相続時精算課税制度利用の流れ
相続時精算課税制度を利用する子または孫は、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要です。戸籍謄本などの一定の書類とともに、贈与税の申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出します。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットと想定されるケースは以下の通りです。
税金の支払いを先延ばしにできる
相続時精算課税制度で財産を贈与すれば、2,500万円までは贈与税がかかりません。また、制度を利用して相続が発生するまで贈与財産に対する税金の支払いを先延ばしにできます。あくまでも支払いの先延ばしであり、税金が免除されるわけではありません。
「生前贈与をしておきたいが、納税を先延ばしにしたい」という希望がある場合であれば、2,500万円までなら贈与税がかからないため、生前贈与を行いやすいでしょう。子どもがまとまったお金が必要なタイミングで生前贈与を行い、税金の支払いを先延ばしにすれば、財産を有効活用できるかもしれません。
収益性のある資産の生前贈与は相続税の節税につながる
相続時精算課税制度で収益を生み出す資産を生前贈与すると、相続税対策につながる可能性があります。たとえば、親が収益不動産を贈与せずに所有し続けると、収益不動産と生前得た家賃収入が相続税の課税対象となります。しかし、相続時精算課税制度で収益不動産を子に生前贈与すれば、贈与後に生じる家賃収入は子に継承できるため、相続税の課税対象に含まれず、収益不動産のみが相続税の課税対象となります。そのため、相続時の収益不動産の時価が贈与時を下回らなければ節税につながります。*
ただし、経年劣化によって贈与後に収益不動産の価値が下がると、価値減少分だけ相続税の負担が増えてしまうので、相続時精算課税制度の選択は慎重に判断する必要があるでしょう。
※家賃収入に対する税金については勘案していません。
将来価値が上がる資産の贈与は相続税対策になる
相続時精算課税制度の贈与財産は、贈与時の時価が相続税評価額となります。そのため、将来価値が上がる資産を贈与すれば、「相続時の時価-贈与時の時価」について相続税の負担が軽減されます。「ほぼ確実に価値が上がる」と見込める資産がある場合は、相続税の節税につながる可能性があります。
そのため、一時的に評価が下がっている自社株など「今後は確実に値上がりする」と判断できる資産がある場合にはメリットがあります。ただし、不動産などは基本的に経年劣化で資産価値が下がります。そもそも必ず値上がりするといえる資産は存在しないため、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かを判断するのは難しいでしょう。
相続時精算課税制度のデメリット
一方で、相続時精算課税制度には以下のデメリットもあります。
年110万円以下の贈与でも贈与税の申告が必要
暦年課税には基礎控除額が設定されており、贈与額が年110万円以下であれば贈与税はかかりません。また、贈与税の申告も不要です。しかし、相続時精算課税制度を選択すると、年110万円以下の贈与であっても、贈与を受けた翌年に贈与税の申告をしなくてはなりません。少額で複数回の贈与を受ける場合は、贈与税申告の手間がかかります。
一度選択すると暦年課税に戻すことはできない
相続時精算課税制度を選択すると、選択した年分以降は永久的に適用され、暦年課税に戻すことができなくなります。暦年課税では、年間110万円までの基礎控除額があるため、計画的に利用することで大きなメリットとなるケースもあるため、相続時精算課税制度の選択は慎重に判断する必要があるでしょう。
小規模宅地等の特例が利用できなくなる
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす土地を相続した場合に、相続税評価額が最大80%減額される制度です。相続時精算課税制度を選択すると、小規模宅地等の特例を利用できなくなります。状況によっては、小規模宅地等の特例の適用を受けることで相続税の節税につながる可能性があります。
国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
まとめ
相続時精算課税制度のメリットがあるケースは限定され、ほとんどのケースでは、暦年課税で少しずつ贈与をするほうが税制メリットは大きいと考えられます。しかし、どうしても生前贈与したいが税金を先延ばしにしたい時などにはメリットがあるでしょう。ただし、一度選択すると暦年課税には戻せないので、相続時精算課税制度の選択は慎重に判断しましょう。