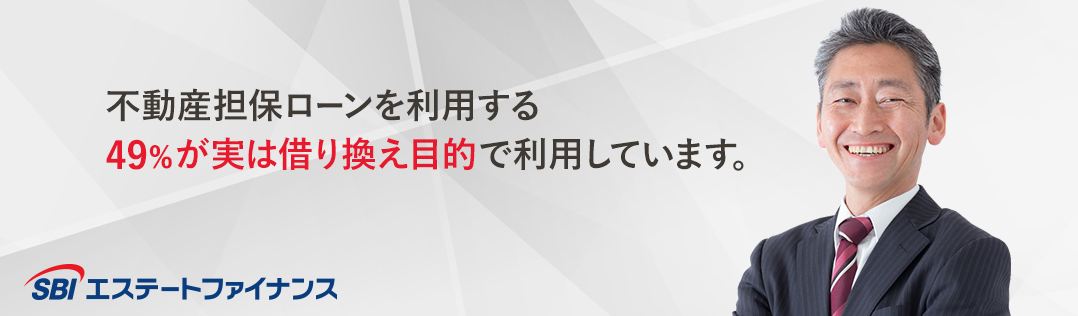平均寿命が延びたことで、「人生100年時代」と言われるようになりました。老後の期間が長くなったのは喜ばしい一方で、老後の生活費の確保が課題になっています。十分な老後資金を準備するには、なるべく早く対策を講じなくてはなりません。節約などの家計改善も有効ですが、一定の収入源を確保することも大切です。そこで今回は、老後に向けて今から準備できる4つの収入源を紹介します。
公的年金
老後の収入源として、まず確保しておきたいのが公的年金(国民年金・厚生年金)です。2020年4月分からの年金額は、国民年金、厚生年金ともに法律の規定により変更があり、国民年金(老齢基礎年金)が満額で月額65,141円です。また、夫婦2人分の標準的な年金額(平均的な収入で老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額)を受け取る場合)は、月額220,724円となっています。公的年金は、一生涯受け取れる終身年金であることが最大のメリットです。
年金額 (出典:日本年金機構「令和2年(2020年)4月分からの年金額等について)
| 令和2年度(月額) | 令和元年度(月額) | |
|---|---|---|
| 国民年金(老齢基礎年金(満額) | 65,141円 | 65,008円 |
| 厚生年金※(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額 | 220,724円 | 220,266円 |
※平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43.9万円)で40年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です
会社員は給与から厚生年金保険料が天引きされますが、自営業者は国民年金保険料を自分で納める必要があります。公的年金を満額受給できるように、保険料の納付漏れがないようにしておくことが大切です。
また、日本年金機構の「ねんきんネット」を利用すると、これまでの年金記録や将来受け取る年金の見込額を確認できます。年金の見込額がわかれば、自分で準備すべき金額が明確になるので、対策を立てやすくなるでしょう。
参考)
・日本年金機構「令和2年(2020年)4月分からの年金額等について」
・日本年金機構「ねんきんネット」
個人年金保険
個人年金保険とは、契約時に設定した期間(保険料払込期間)にわたって保険料を払い込むことで、一定期間(5年、10年など)年金を受け取れる貯蓄型保険です。個人年金保険に加入すれば、公的年金の不足分を補うことができます。
万が一、年金の受取開始前に契約者にもしものことがあれば、払込保険料に応じた死亡保険金が支払われる仕組みで、年金の受取期間中に受取人が亡くなった場合は、遺族に年金が支払われます。
個人年金保険は、毎月保険料を支払うことで、半強制的に老後資金を準備できるのがメリットです。また、一定金額までの保険料は生命保険料控除の対象なので、所得税・住民税の節税にもなります。
ただし、低金利の影響で予定利率が下がっているため、保険料を長期間支払ってもお金はそれほど増えません。さらに、保険商品はインフレに弱く、物価上昇により払込保険料が実質的に目減りする恐れがあることや、中途解約すると元本割れの可能性もある点には注意が必要です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCo(イデコ)とは、自分で掛金を拠出し、自分で運用方法を選んで掛金を運用する私的年金制度です。定期預金や投資信託などから運用商品を選択して運用を行います。60歳になるまで掛金を拠出し、60歳以降に老齢給付金を受け取る仕組みです。以下のように、加入区分に応じて掛金の上限額が設けられています。
- 自営業者:月額6.8万円(年額81.6万円)
- 会社員:月額1.2万円~2.3万円(年額14.4万円~27.6万円)
- 公務員:月額1.2万円(年額14.4万円)
- 専業主婦(夫):月額2.3万円(年額27.6万円)
また、iDeCoには、以下3つの税制メリットが用意されています。
- 掛金が全額所得控除
- 運用益は非課税
- 給付を受け取るときの税制優遇措置
iDeCoは掛金が全額所得控除で、運用益も非課税になるため、効率的に資産を増やせます。給付を受け取るときの税制優遇措置もあり、一括で受け取る場合は「退職所得控除」、年金で受け取る場合は「公的年金等控除」が適用されます。
ただし、iDeCoの掛金は、原則60歳になるまで引き出すことができません。掛金を増やしすぎると手元資金が不足する可能性があるので、無理のない金額で掛金を払い続けることが大切です。
小規模企業共済
小規模企業共済とは、自営業者や経営者のための退職金制度です。廃業や退職時に備えて積み立てができ、月々の掛金は1,000円~7万円まで500円単位で自由に設定できます。加入後の増額・減額も可能です。掛金は全額所得控除で、共済金を受け取るときも退職所得控除や公的年金等控除が適用されます。
将来受け取る共済金は、請求事由によって種類が異なります。たとえば、個人事業主の場合、個人事業の廃業は共済金A*に該当し、掛金を上回る共済金を受け取れます。任意解約も可能ですが、基本的には元本割れとなります。また、加入後12か月未満で解約すると、掛金が戻ってこないので注意しましょう。
※共済金Aとは、共済金等の種類の一つです。詳しくは下記参考リンクをご確認ください。
参考)独立行政法人 中小企業基盤整備機構「小規模企業共済とは」
その他の資産運用
老後に向けて資産を増やすには、株や不動産などの資産運用に取り組むのもひとつの方法です。どちらもインフレに強い資産で、物価上昇時には株や不動産の資産価値も上昇する傾向にあります。
株式投資は、値上がり益や配当を目的に個別銘柄に投資する以外に、少額から分散投資ができる投資信託を活用する方法もあります。株式投資の経験がない場合は、運用をプロに任せられる投資信託を検討するといいでしょう。また、近年はロボアドバイザーなどのサービスもあります。
不動産については、収益用不動産を購入して家賃収入を得る方法が一般的です。しかし、低金利の住宅ローンを利用して自宅を購入することも、考え方によっては資産運用と言えるでしょう。老後に住宅ローンを完済した自宅があれば、そのまま住み続ける以外に「売却してまとまったお金を手に入れる」「自宅を担保にお金を借りる」など、資金調達手段としても活用できます。
まとめ
ここまで紹介してきたように、老後に収入源を確保する方法は複数あります。短期間でまとまったお金を作るのは難しいので、なるべく早く準備を始めることが大切です。まずは公的年金の見込額を確認することから始めてみるといいでしょう。