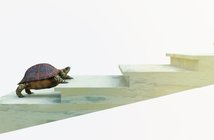先の展開が上値重くても上昇する理由
投機は、将来的に価格が上昇するか否かに沿う格好になるように、現在の仕掛けを判断しているわけではありません。毎年繰り返される経済活動による資金移動を利用して、値幅の伴った価格の大きな振れを作っています。
前述した通り、日経平均株価が弱気の流れを作る年は、年の前半から下降を開始する年もありますが、よく見られる展開は、強気材料出尽くしとなる4~6月までの期間で、年間の最高値をつけて、下降を開始する展開です。
投機は、上下どちらでも大きく動いてくれればいいだけです。
その年の後半に価格が下げる可能性があるとしても、積極的に売りを入れられる状況へ入らないなら、下降への振れ幅を大きくする作業として、強く上値を抑えられる場所を探る動きになります。
個別銘柄では、将来の業績悪化が明確になっているものが、積極的に買われることがほとんどありませんが、投機の対象になっている銘柄は、将来的に明確な弱気材料があっても、短期的に上昇することで、下げ方向の振れ幅を大きくできるなら、その作業を実行します。
これまでは、人の思惑の中で、その作業が行われてきたため、行ける場所にも限度がありました。
戻り高値を試す場合でも、これ以上へは行き難いという場所があるなら、その十分手前で止まり、上値を抑えられる動きが見られました。そのため、半値戻し、3分の2戻しなど、人の考える範囲内でのテクニカル的な上値の目安が役に立ってきたわけです。
しかし、現在は、“行けるところまで”という目安が変化しているように感じます。
前述した通り、以前は、人の思惑の中で、警戒感を強く感じる場所で、価格が強く上値を抑えられる動きになりました。そのため、前述したようなテクニカル的なポイント、多くの市場参加者が目安にしている場所で、上値を抑えられる動きがあらわれてきました。
現在は、そのような人も思惑による警戒感などなく、一定の条件のもとで、勝手に取引がなされています。そのため、上値の抑えられる可能性のある場所は、過去の経験則から人が警戒感を感じる場所ではなく、特定の時間、日にち、特定の値位置のギリギリを試すことのできる状況になっています。
これまでは、ある高値が戻り高値になっているなら、この地点まで上昇しないだろうと推測できる場所だったとしても、そこを簡単に抜けて、なんの兆しもなく、想定していた戻り高値が意識されて、結果として下げているという展開になっています。
そのため、近い将来に価格が下げるとしても、その日、下げられないのであれば、翌日以降、価格が下げるとき、より大きな値幅を取るため、その日の価格がなるべく上昇するように仕向けられるという動きがあらわれているように見えます。