個人消費 記事一覧
-

中国が「若者のクルマ離れ」を阻止。日本が学ぶべきZ世代向け戦略=牧野武文
今まで車に興味のなかった中国の若者たちが、車を欲しがるようになってきました。それはなぜか?日本企業も参考にすべき中国メーカーの戦略を解説します。
-

「長寿リスク」コロナで浮き彫り。守りに入る国民、消費の重石に=久保田博幸
9月日銀会合の議事要旨が11月4日に公表された。このなかの日本景気の先行きについて、コロナ禍によって年金不安や長寿リスクが意識されたとの意見がある。
-

なぜ日本だけ消費が戻らないのか?米国と中国はすでに前年水準を回復=吉田繁治
米国と中国の消費支出は前年水準を回復した一方、日本は前年比−7.6%とダメージを受けたままです。いったいその原因は何なのか?総務省データから紐解きます。
-

コロナは何も壊していない。急速な景気悪化は人為的に行ったものの結果=久保田博幸
コロナショックは自然災害に似ている。ただ巨大地震は物を破壊するが、今回は家も工場もインフラもそのままだ。脅威が後退すれば、元の経済活動に復帰できる。
-
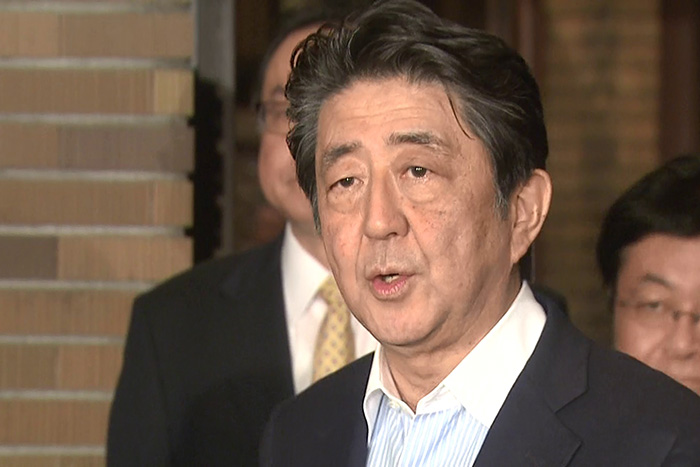
なぜ日本人の給料は上がらない? 世界との比較で見えた日本「ひとり負け」の現状=斎藤満
世界と比較しても、日本の実質賃金は異常な減少傾向にあります。消費増税で消費が落ち込んでいますが、その前からの賃金低下でモノが買えない状況です。
-
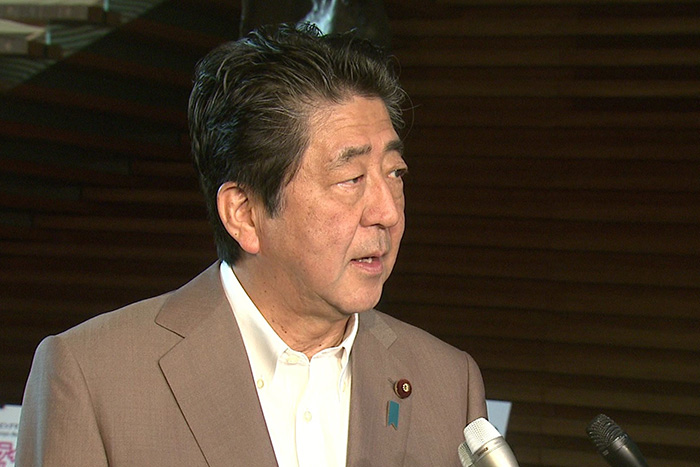
消費増税は最悪のタイミング。低所得者と老人の生活を壊し、企業と富裕層を喜ばせる愚策=斎藤満
10月から消費税が10%に引き上げられる予定です。タイミングとしては最悪で、とくに低所得者や年金暮らしの高齢者には、生活破壊的な影響があります。
-

政府はもう「戦後最長の景気拡大」と言い張れない。1~3月はゼロ成長へ=斎藤満
政府の「戦後最長の景気拡大」認識はこのところ旗色が悪くなりました。そこで今回は1-3月の実質GDP成長率予想を試みます。日本経済の実態はどうでしょうか。
-

米国民の半分は2007年時点よりも貧乏に。これから伸びる理由がない米国経済
米国ミネアポリス地区連銀の調査によると、米国民の半分は「2007年時点よりも貧乏」になっているようです。これでは今後の消費やGDPの伸びは期待できません。
-

没落する米国の中流階級。マクドナルドの低価格戦略で実感した超格差社会
米マクドナルド社の販売戦力とその成功を見ると、米国でも中流階級がいなくなっていること、つまり低所得者と富裕層の2極化が進んでいることがよくわかります。
-

「今年のクリスマスプレゼントは安物にしておこう」米年末商戦に異変アリ
毎年盛り上がりを見せる米国の年末商戦。強気な株式市場と低い失業率のなか、なぜか今年は昨年よりもプレゼントの金額が低くなるという報道がされている。
-

「老後不安による消費低迷」がトンデモ理論かもしれない最大の理由=藤井聡
経済の大御所2名がレポートを公表し、消費低迷の要因は「賃金の上昇不足」と「将来不安」だと断定しています。これはフェイクレポートと言わざるをえません。
-

意外な真理?「10万以上のモノは、欲しいと思ったときが買い時」に共感の声続々!
ものすごく欲しいものがあっても、その値段があまりに高いと買うべきか我慢するべきか悩んでしまうもの。しかし、そんなときは「買うのが正解」らしい!?
-

いざ衆院解散!日本が「消費増税」で選べる3つのオプションとは?=内閣官房参与 藤井聡
衆院解散の大義として「消費増税」が注目されています。この増税には3つのオプションがあり、どれを選ぶかで日本の未来は大きく左右されるのです。
-
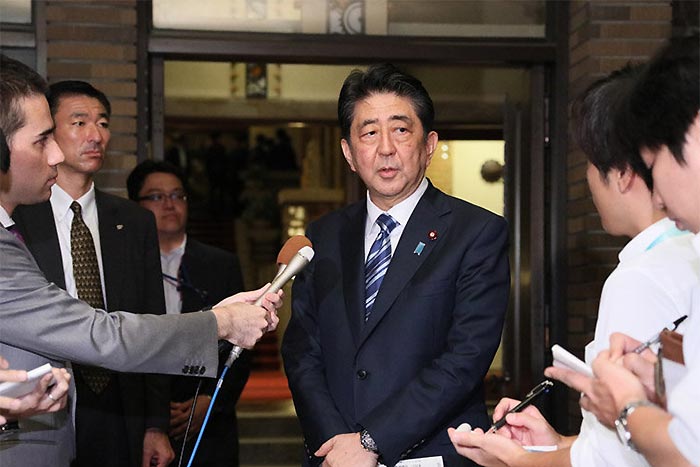
安倍内閣がひた隠す景気後退「いざなぎ詐欺」の忖度と不正を暴く=斎藤満
政府が「戦後2位のいざなぎ景気に並ぶ景気回復」をアピールしています。しかしこれは、安倍政権の意向を忖度した内閣府の不正による「偽りの成果」です。
-

値下げイオンvs値上げ鳥貴族。「回復する個人消費」駆け引きの勝者は?=斎藤満
政府がいざなぎ景気並の景気拡大をアピールする中、企業の価格戦略にも多様性が生まれています。今、日本の個人消費はどこまで回復しているのでしょうか?
-

日本はなぜ超格差社会になったのか?その「制裁」は1989年に始まった=矢口新
日本社会の格差が固定化、拡大を続けている。負担の大きい中間層はさらに没落しつつある。我が国は実質的な「経済制裁」を受けているも同然の状態だ。
-

親日国家「15億人マーケット」に進出してこそ日本経済は復活する=炎
中国や韓国は経済成長の前段では日本にすり寄り、自国の経済成長を成し遂げると手のひらを返しました。日本がこの先も発展するためには、親日国との連携を強めるべきです。(『億の近道』炎のファンドマネージャー) プロフィール:炎の
-

円高は本当に悪なのか?今、日本人に笑顔が戻りつつあるという皮肉=斎藤満
円高、物価下落に救われた個人消費。日銀の総括検証を機会に、アベノミクスも、円安や物価高を目指すことが日本経済のために本当に良いのか等、総点検する必要があります。
