物価 記事一覧
-

大規模緩和の行き着く先は食料難。職と家を失う国民を物価上昇が襲う=斎藤満
コロナで職を失った人々の多くが食料難民となりかねない一方で、金融緩和マネーによって食料価格が上昇しやすい状況にあります。きめ細かな支援が必要です。
-

サンマが高い。サバやマグロは? 50年の価格推移で見えた低インフレの実像と景気悪化=高梨彰
サンマの価格が依然として高め。2年前の不漁時には約5割高で、今年も似た雰囲気です。とはいえサンマは「物価の優等生」。サバやマグロはどうでしょうか。
-

また忖度。勤労統計「データ改ざん」で露呈した見せかけの賃金上昇と雇用改善=斎藤満
厚生労働省発表の「毎月勤労統計」でインチキが露呈。人件費も雇用も改善していない事実がわかり、安倍政権の「データ改ざん」体質が浮き彫りにされました。
-

「給料上がってない」は一部の人の感想なのか?麻生氏暴言と矛盾するGDPマイナス成長=今市太郎
麻生氏は景気拡大期が「いざなぎ景気」を超えたが賃金が上がっていない状況を問われ、「上がっていないと感じる人の感性」との見解を示し物議を醸しています。
-

景気の下振れリスクについて言及した日銀に、打つ手はあるのか?=高梨彰
黒田東彦日銀総裁は「リスクが増せば政策対応」をすると言っています。しかし、いまの日銀にどのような政策対応の手段が残されているでしょうか。
-

なぜ日本の物価は上がらない。言い訳探しを始めた黒田日銀が見抜けなかったこと=斎藤満
日銀の黒田総裁が「物価が上がらない」4つの理由を挙げています。日銀は需給ギャップが改善していると言いますが、実態はまったく違うのではないでしょうか。
-

物価2%を諦めた日銀が、欧米から学ぶべきこと~そもそも上がるボーナスがない日本人=児島康孝
日銀はどうやら「物価2%」を諦めたようです。デフレはより深刻化し、夏のボーナス上昇の報道も、そもそももらえない日本人が増えているのが実状です。
-

金融市場は「安倍退陣」を現実のシナリオとして意識し始めた=近藤駿介
安倍総理にとっては内憂外患による失地挽回を賭けた日米首脳会談だが、失敗といえるだろう。市場は「安倍退陣」を現実のシナリオとして意識していくことになる。
-

4月からまた値上げ……日本の「体感」物価上昇はもうとっくに2%を超えている=斎藤満
この4月から瓶ビールや納豆、牛丼などが値上がりしています。国民の体感インフレ率がとっくに2%を超えるなか、物価上昇の中身にも変化が出てきています。
-
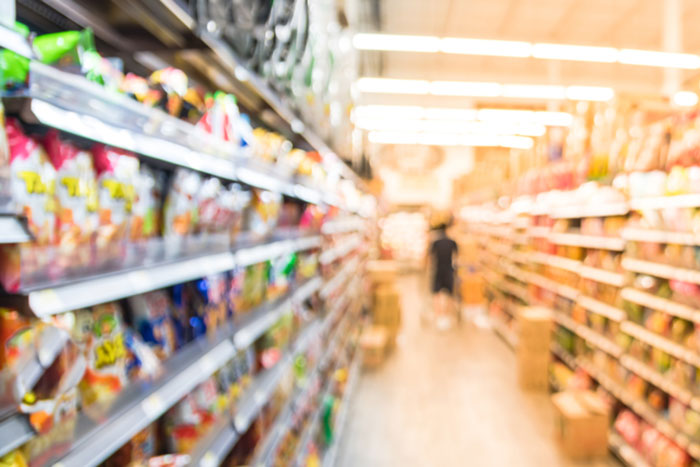
FPとして考えた「#くいもんみんな小さくなってませんか日本」対策=川畑明美
Twitterで「#くいもんみんな小さくなってませんか日本」が流行っています。確かに食品の容量が減っており、これが日本経済に悪循環をもたらしています。
-

2018年の相場を予想しつつ「今年っぽいポートフォリオ」を考えてみた=田中徹郎
年頭恒例「2018年型ポートフォリオを考える」です。今年の重要ポイントと地域別経済予測、各種相場の流れと投資スタンス、推奨ポートフォリオを解説します。
-

野菜の異常な値上がりが「日本復活のシグナル」かもしれないワケ=児島康孝
野菜が高騰しています。このことは一見、台所を直撃する「良くないニュース」に見えます。しかし実は、日本のデフレが終わろうとしているというサインです。
-

「いざなぎ景気超え」の日本で、黒田日銀が見落とした2つの変化=田中徹郎
「いざなぎ景気超え」の日本で、なぜ物価が上がらないのか?日銀の2%インフレ目標は存在意義を失いつつあるばかりか、新たなバブルの種にもなりえます。
-

値下げイオンvs値上げ鳥貴族。「回復する個人消費」駆け引きの勝者は?=斎藤満
政府がいざなぎ景気並の景気拡大をアピールする中、企業の価格戦略にも多様性が生まれています。今、日本の個人消費はどこまで回復しているのでしょうか?
-

内閣府データが示す、10~15兆円規模の大型補正予算の必要性=内閣官房参与 藤井聡
デフレ脱却のため、政府は10~15兆円規模の大型補正予算を組むことが是が非でも求められています。そのことは内閣府自身の公表データからも見て取れます。
-

Fedウォッチャーのグレッグ・イップが警告する「景気後退」4つの前兆=高梨彰
影響力のあるFedウォッチャーの1人、WSJのグレッグ・イップ氏が「景気後退前夜」の条件を挙げました。そして現状はこの条件に該当すると指摘しています。
-

【大本営発表】「いざなぎ景気超え間近」がウソである3つの理由=小浜逸郎
政府がまとめた景気動向調査では、現在は「いざなぎ景気」並の好景気とのこと。何を見てそう判断したのか庶民にはまったく実感がありません。つまり大ウソです。
-

日本人の賃金はなぜ「バブル期以来の人手不足」でも伸びないのか?=斎藤満
政府が雇用賃金の改善を宣伝するのと裏腹に、賃金の低迷が続いています。日米共通の奇妙な現象ですが、日本は数字以上に実態が悪いという「おまけ」つきです。
-

じゃがいも不足で販売休止、ポテトチップス大手「次の一手」は?=佐藤昌司
原料のジャガイモ不足で店頭から次々と姿を消しているポテトチップス。カルビーや湖池屋などポテトチップスを主力とする企業は、今後どんな手を打ってくるのでしょうか。
-

ヤマト運輸の「悲痛な値上げ」をもたらしたアベノミクスの限界=島倉原
ヤマト運輸が運賃引き上げの方針を固めました。問題となったトラック運転手の低賃金・長時間労働の背景には、緊縮財政による日本経済全体の長期停滞とデフレがあります。
