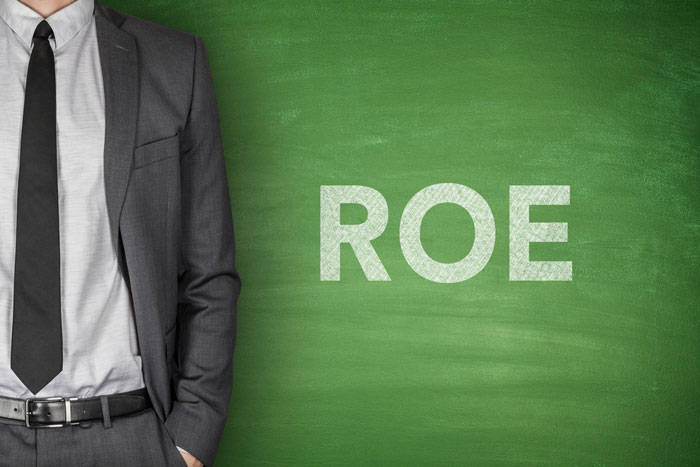日銀ETF購入で「高まる緊張感」と「失われる緊張感」
「JPX日経400の登場後、指数への採用・非採用を問わず企業側にも資本効率を重視した取り組みが目立っている。積極的な自社株買いや配当など新たな資本政策を打ち出したアマダ、17年3月期までにROEの20%超への引き上げを目指すミネベアなどだ」(20014/8/27 Bloomberg 「JPX日経に4:4:2の妙、開発者が求めた理念と実用性」)
GPIFのベンチマークとなるJPX日経400が登場を契機に、多くの企業がROEを高める策を打ち出し始めています。これは、企業サイドに「指数に採用されないと投資して貰えない」という緊張感が生じたからです。
日本版スチュワードシップ・コードを受け入れた日本の機関投資家が、「赤字が続いて無配当」であっても投資してくれるお人好しの投資家で居続ける限り、株主総会で否定される可能性の低い議案にいくら反対票を投じても、「企業と投資側の緊張感」など高まりようがないというのが現実です。
さらに、GPIFを筆頭に日本の機関投資家の運用は年金も投信もベンチマーク運用が主流になって来ていますから、ベンチマークに採用される株価指数に採用されている限り、機関投資家の投資対象から外れる可能性は低い状況にあります。
さらに、日本銀行が株価指数に連動するETFを年間3兆円も購入することを表明していますから、特定の銘柄の株価だけが大きく下落する可能性は低くなって来ています。
つまり、世の中の運用がベンチマーク運用に偏って行く中で、中央銀行はベンチマークに連動するETFを大量に購入することで、日本版スチュワードシップ・コードの策定によって「企業と投資側の緊張感」を高めようとする動きに逆行して、「企業と投資家側の緊張感」を高める阻害要因を提供しているということです。
政府と日銀が合体して上昇相場を演出してくれることによる「市場と投資家側の緊張感」の喪失は、機関投資家の運用能力向上を阻むことを通して、日銀によるETF購入終了後に「投信購入者と運用会社との間の緊張感」という新たな緊張感を招く要因となりそうです。
『近藤駿介~金融市場を通して見える世界』(2015年6月17日号)より一部抜粋
※太字はMONEY VOICE編集部による
無料メルマガ好評配信中
近藤駿介~金融市場を通して見える世界
[無料 ほぼ 平日刊]
ファンドマネージャー、ストラテジストとして金融市場で20年以上の実戦経験を持つと同時に、評論家としても活動してきた近藤駿介の、教科書的な評論・解説ではなく、市場参加者の肌感覚を伝えるマガジン。