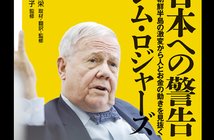支給開始後も目減りが続く
問題は、30年後に今の若者が年金を支給される際に、所得代替率が50%強、つまり現役世代の手取りの半分を支給されるとしても、その比率が以後も保証されるものではないことです。支給開始から20年、30年と経つうちに、この所得代替率はさらに低下して、いずれ現役世代の手取りの半分以下になります。
そしてもう1つ、支給される年金額はすべて使える「手取り額」ではなく、ここから税金や社会保険料(介護保険料など)を払います。現役世代の「手取り額」に対して51.9%とか、46.1%とか言っても、年金受給者はここから税や介護保険料など社会保険料を払うので、同じ手取りベースの所得代替率はさらに低くなり、現役の半分には遠く及ばない額しか使えません。
非正規の無年金予備軍
さらに、この財政検証の前提は、労働者が60歳まで年金保険料を払うことを前提にしています。
しかし、最近は労働者の4割近くが非正規雇用になっています。政府が率先して非正規雇用を推進したのは、企業が社会保険料負担を回避し、企業の人件費負担を抑えるためでした。裏を返せば、この制度のおかげで、パートタイマー労働者など多くが厚生年金に加入してもらえず、働いても年金をかけていない人が少なくないことです。
これは将来の「無年金」生活者の予備軍となり、この不十分な年金制度そのものにも入れなく、生活の保障がまったくない人がいずれ大量に排出される可能性を示唆しています。
この脅威を指摘されてか、政府の手違いで「消えた年金」の被害者が多く出たためか、政府は年金受給資格を緩和して、従来25年以上の年金支払いを要件としていたところから、10年以上支払った人にも受給資格を与えることにしました。
これによっていわゆる「無年金」者は減りますが、それでも10年働き、年金を支払った人がもらえる年金は、基礎年金と老齢厚生年金とを合わせても現時点で年40万円前後、月額3万円強で、さらにここから介護保険料が年に5万円余り引かれます。生活保護世帯よりもさらに悲惨な状況で、とても自立した生活はできません。