大局観は「長期的な強いインフレ」
今回は、今年最後のメルマガ(2016年12月25日号)なので、個人的に考えている、長期的な投資戦略について書いておきます。1年以上先のことは妄想なので、そのつもりで読んでください。
これから先のポイントは、長期的に強いインフレ局面へ入り、それを継続するということです。
強いインフレと書くと、すぐに「じゃあ来年からハイパーインフレになるのか」と、極端に解釈する方がいるのですが、そうではありません。
2016年、FRBは4回の利上げを予定していましたが、結局、年末に一度だけしか実行できませんでした。中国経済の低迷や、イギリスの国民投票でのEUの混乱、不安定な中東情勢など、世界全体に不安要因が多く、利上げする環境にならなかったためです。そのような状況で、来年からハイパーインフレになるわけがありません。
イエレン議長が、FOMC後の記者会見で「来年3回の利上げを予定している」と述べたように、2017年以降、緩やかな金利の上昇局面へ入ってゆくと考えられます。詳細な経緯は後述しますが、2017年以降、数年間の緩やかなインフレを経過し、その後、インフレ圧力が強まる中で、それをコントロールできなくなり、陰謀論者が大好きな高インフレ局面へ入ると見ています。
その流れの中で、国内の値幅で利益を得るための有効な投資先は、
「2017~18年 日本株、買い」
「2017~20年 商品先物市場、買い、特に金」
「2020年以降 中央銀行の発行する仮想通貨、買い」
(極端に書くと、もっと先に紙のお金が紙くずになることを想定して事前に交換しておくという感じです)
を考えています。
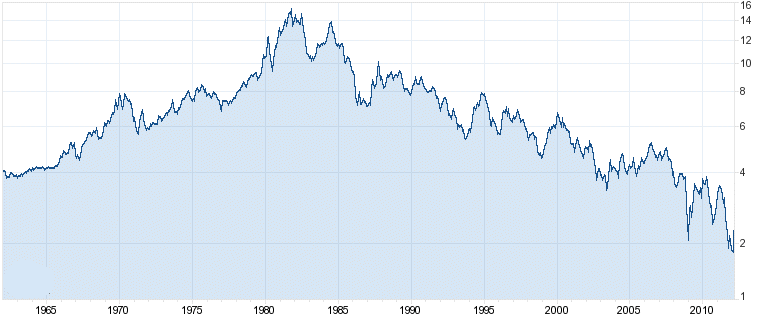
図: 米国10年債利回りの推移
図は、1960年から2012年頃までの米国10年債利回りの推移を示したグラフです。終戦後の混乱期を経て、ブレトン・ウッズ体制(ドルを基軸通貨として、1オンス35ドルと定め(金本位制)、ドルと各国通貨を固定した交換比率とした)のもと、安定した為替相場の中で、米国経済は、1950~60年代、高い経済成長、低失業率を実現しました。
図の米国債利回りは、60年から65年くらいまでは、4%以下から少しずつ4%を超える程度まで上げている程度の動きになっています。米国は、60年半ば頃には完全雇用の状態へ入り、緩やかなインフレ傾向へ入っていました。
そのような状況では、財政の出動を抑えて、お金の循環を抑制してゆく必要がありますが、65年以降、ベトナム戦争へ深入りしてゆく過程で、軍事費を大幅に拡大しました。その結果、65年以降、徐々にインフレ傾向が強くなり、図1のグラフでは、65年から70年までの期間で、米国10年債利回りが4%から8%まで上昇しています。
軍事費の拡大だけが理由ではありませんが、結局、この時期の財政拡大でドルの供給量が増加し、金との交換を米国が保証できない状況へ陥ったため、71年にニクソン大統領が金とドルとの交換停止を発表し、73年に主要国が変動相場制へ移行し、ブレトン・ウッズ体制が完全に崩壊します。
米国経済を語るメルマガではないので、端折りますが、世界的に高いインフレ率が定着してしまう状況の中で、73年の第四次中東戦争、78年のイラン革命をきっかけにした原油高騰がインフレを加速させた結果、米国10年債利回りは、81年に15%を超えてしまいます。













